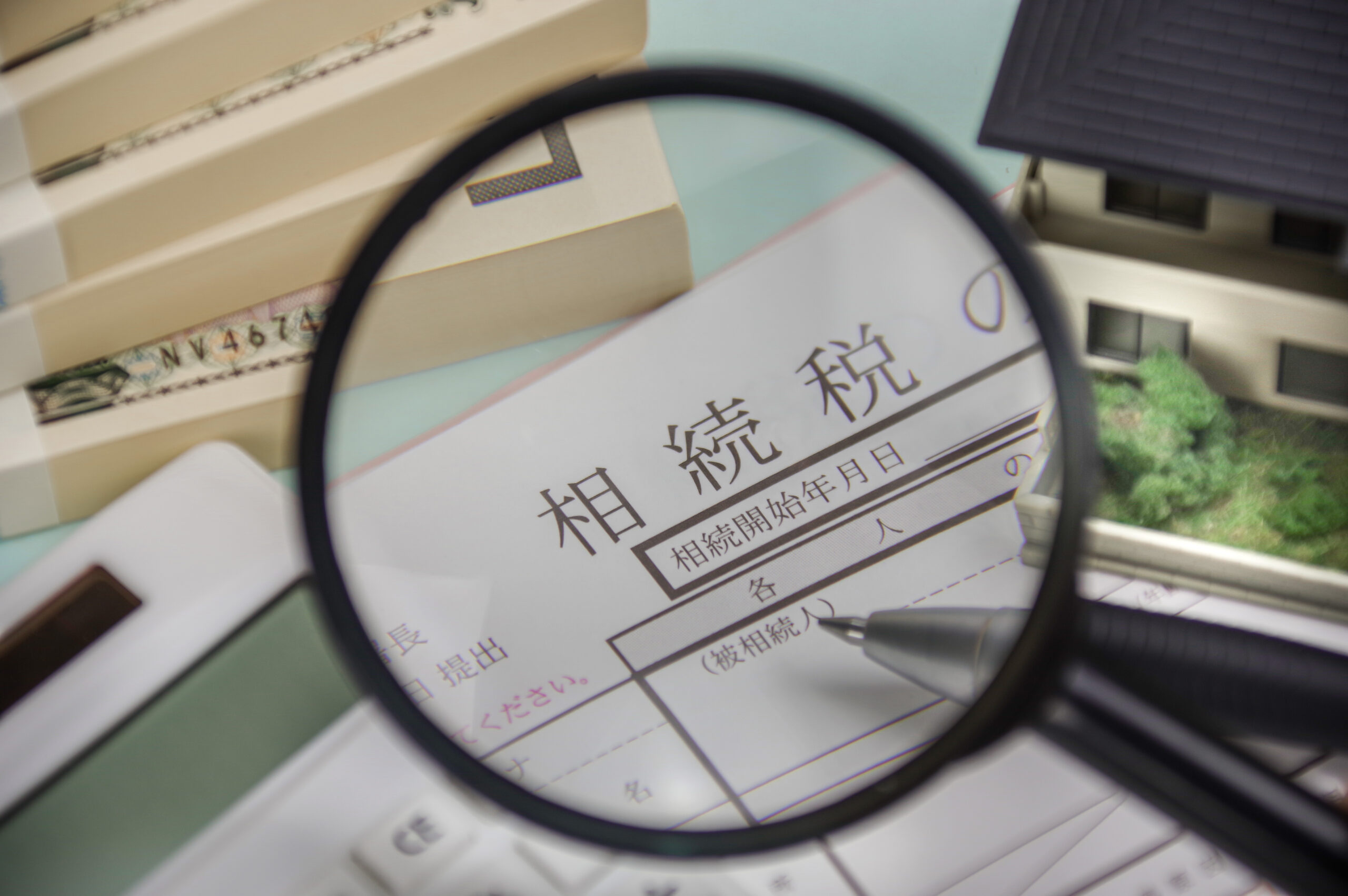ご両親が亡くなって戸建住宅やマンションを相続したものの、相続税に不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。自己資金での相続税納付が難しい場合、相続不動産の売却代金を充当する方法が有効です。
不動産売却時にはさまざまな税金がかかりますが、相続税納付を目的とした売却では、特例を受けられる可能性があります。
この記事では、不動産売却時にかかる税金を紹介するとともに、相続税納付のための売却で使える譲渡所得税の特例について解説します。
相続不動産にかかる相続税の基本知識
経済的に相続税を納付するのが難しいと考え、相続不動産の売却を検討中の方もいるかもしれません。しかし、そもそも相続税が課税されないケースも多くあります。まずは、相続税評価額の求め方や納付期限など、不動産にまつわる相続税の基本知識を確認しましょう。
相続不動産の相続税評価額
不動産にかかる相続税は、土地・建物それぞれの相続税評価額に税率をかけることで求められます。税額計算のベースとなる相続税評価額の求め方を紹介します。
土地の相続税評価額
土地の相続税評価額は「路線価方式」によって求めるのが基本です。路線価とは、道路(路線)ごとに設定される土地価格のことで、その道路に面する土地1m2あたりの価格を表します。国税庁が毎年7月に公表しており、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で確認できます。路線価方式で土地の相続税評価額を求める計算式は次のとおりです。
旗竿地や台形などの不整形地、奥行きのある敷地などの利用しにくい土地については、補正率をかけて減額する仕組みです。
ちなみに、路線価は「地価公示価格の8割」をベースに設定されます。一方、土地の時価(実勢価格)は地価公示価格の1.1〜1.2倍程度が目安とされています。これを踏まえると、路線価の目安は時価の6〜7割程度。時価を基準に相続税が課税される金融資産と比較して、土地は相続税を抑えやすい資産といえるでしょう。
建物の相続税評価額

建物の相続税評価額は、基本的に固定資産税評価額と同額です。固定資産税評価額は、不動産所有者へ毎年郵送される「固定資産税納付通知書」に添付の「課税明細書」に記載されています。故人の遺した書類があれば、それを確認するとよいでしょう。課税明細書が見つからない場合、自治体の窓口で固定資産課税台帳の閲覧を申請するか、固定資産税評価証明書を請求すれば評価額を確認できます。
なお、建物の固定資産税評価額も時価と比較して低い水準に抑えられているため、建物も土地と同様に相続税を抑えやすい資産といえるでしょう。
相続税はいつまでに納める?
相続税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、現金で納めるのが原則です。つまり、通常は親の亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に、相続税分の現金を準備しなければならないということになります。納付が遅れると、遅延日数に応じた延滞税が課されるため注意しましょう。
後ほど紹介する譲渡所得税の特例は、相続開始日の翌日から適用できる決まりになっています。そのため、現金を準備できる見込みがない場合、なるべく早めに売却を検討するのが得策といえるでしょう。
売却検討前に確認しておきたい相続税の基礎控除額
相続税納付を目的に相続不動産の売却を検討する前に、そもそも相続した遺産に対して相続税がかかるのかをしっかり確認しておきましょう。
というのも、相続税の課税割合は全体の10%弱(2023年分)に過ぎず、実に9割の相続人には相続税が課税されていません。なぜなら、相続税には基礎控除が設けられており、相続遺産の合計評価額が基礎控除以下であれば課税対象にならないからです。
上記の計算式より、不動産とそれ以外の相続遺産を合わせた評価額が3,600万円以下であれば、法定相続人の人数に関わらず、相続税は発生しないことになります。先述のとおり、土地や建物は金融資産と比較して評価額が低くなる傾向にあるので、実際には相続税がかからないケースも多いのです。
ただし、相続税の計算は複雑かつ専門知識を要するため、自分だけで判断せず、税理士や相続不動産の取り扱い実績が豊富な不動産会社などの専門家に相談すると安心です。
相続税納付のための不動産売却時にかかる税金や費用
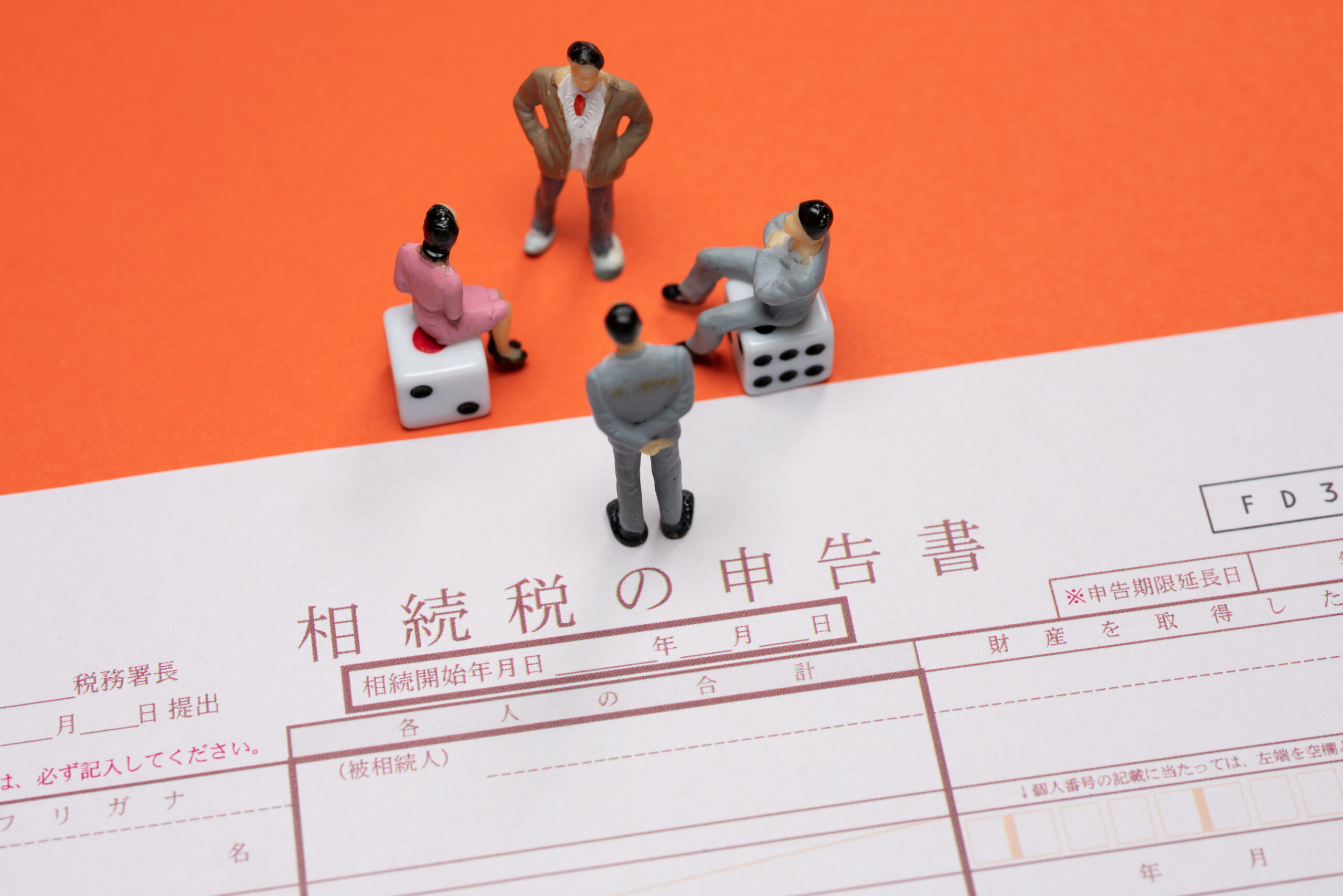
相続税を納付しなければならないケースで、納付を目的として不動産を売却するときには、次に挙げる税金や費用がかかる可能性があります。
- 譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)
- 印紙税
- 登録免許税
- 仲介手数料
ここでは、各費用の詳細を解説します。
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)
不動産売却で得た譲渡所得に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。これらを総称して、一般的に「譲渡所得税」と呼びます。課税対象が売却益ではなく、譲渡所得となっているのがポイントです。
その不動産の所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、それぞれ異なる税率が設定されています。ただし、相続不動産では、故人の取得日から所有期間を計算できると定められているため、多くのケースで長期譲渡所得として扱われるでしょう。
| 売却年の1月1日時点での所有期間 | 合計税率 | |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
譲渡所得税は、不動産売却時にかかる税金の中でも特に負担が大きいものです。しかし、相続税納付目的の売却では、後で紹介する特例を利用できます。
印紙税
不動産の売買契約締結時、契約書に印紙を貼付する形で納めるのが印紙税です。通常、契約書は2通作成し、売主・買主それぞれに印紙税を負担するのが一般的です。2027年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書(売買契約書)に関しては、軽減税率が適用されます。
不動産の売買契約書にかかる印紙税率(一部抜粋)
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
登録免許税
相続不動産を売却するには、事前に「相続登記」を行い、所有権を被相続人(故人)から相続人へと移転させておく必要があります。相続人が相続登記を行う場合、登録免許税として「固定資産税評価額×0.4%」を納めなくてはなりません。
ただし、築年数の古い空き家などで課税標準額が100万円以下の場合、2027年3月31日まで免税措置が適用されます。
仲介手数料
不動産会社の仲介で相続不動産を売却した場合、売却価格に応じた仲介手数料を、不動産会社へ支払う必要があります。仲介手数料は宅建業法で上限額が定められており、その範囲内で不動産会社が自由に設定可能です。
不動産売買における仲介手数料の上限額
| 売却価格(税抜) | 本則税率 |
| 200万円以下 | 売却価格(税抜)× 5%+税 |
| 200万円超400万円以下 | 売却価格(税抜)× 4%+2万円+税 |
| 400万円超 | 売却価格(税抜)× 3%+6万円+税 |
相続税納付のための不動産売却で使える譲渡所得税の特例2選

不動産売却時にかかる税金の中でも、特に大きな金額を占めるのが譲渡所得税です。しかし、相続税納付のための売却においては、譲渡所得の特例を活用できる可能性があります。ここでは、代表的な2つの特例の内容を解説します。いずれも売却までの期限が設けられている点に要注意です。
①相続税の取得費加算の特例
「相続税の取得費加算の特例」は、不動産の相続人が、相続税の課税を理由にその不動産を売却する場合に受けられる特例です。具体的には、相続開始から一定期間内に売却したとき、相続税額の一部を不動産の取得価格に含めることができます。これにより、課税対象の譲渡所得を小さくできるのです。
「相続税の取得費加算の特例」適用の3要件
- 相続・遺贈で財産を取得したこと
- 財産を取得した人が相続税を納付していること
- 相続税申告期限の翌日から3年以内に売却すること
取得価格に加算できる金額は、次の計算式で求められます。
②被相続人の空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例
被相続人である親などが亡くなるまで居住していた家が、相続によって空き家になった場合に受けられるのが「被相続人の空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」です。適用を受けるには、以下の要件をすべて満たしている必要がありますが、当てはまれば譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
「被相続人の空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」の主な要件
<建物の要件>
- 1981年5月31日以前に建築されたこと
- 売却時に一定の耐震基準を満たしていること
- 区分所有のマンションでないこと
- 相続開始直前に被相続人が一人暮らしをしていたこと
- 相続から売却までの間に空き家だったこと
<適用要件>
- 相続または遺贈を受けた人が売却すること
- 相続開始日から3年が経過する年末までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
まとめ
不動産を相続したときは、まず相続税の課税対象となるかどうか確認しましょう。課税対象となるケースで、納付できるだけの経済的余裕がない場合には、相続不動産の売却代金を相続税納付に充てるというのも一つの方法です。
相続不動産の売却で利益が発生すると譲渡所得税がかかりますが、一定の要件を満たせば特例が適用できます。今回紹介した譲渡所得税の特例を受けるには、相続開始から3年以内をメドに売却する必要があるため、早めに売却活動をスタートすることが大切です。
横浜で相続不動産の売却をご検討中なら、横浜エリアに特化して売却をサポートする「横浜スタイル」へぜひご相談ください。売却だけでなく、遺産分割協議や相続登記といった相続関連の手続きも、士業のプロと連携しながらトータルでサポートいたします。